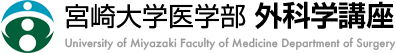よくある質問:消化管・内分泌・小児外科
- なぜ小児外科医が必要なのか?
-
「こどもはおとなのミニチュアではない」 小児外科を説明するときによく使われる言葉ですが,これほど適切に小児外科の特質をあらわした言葉はありません.
こどもはおとなに比べてからだが小さく,とくに新生児・未熟児では非常に繊細な手術のテクニックが必要です.おとなの手術と同じ方法ではこどもの手術は行えません.
しかしもっと大事なことは,こどものからだはおとなのように完成したものではないことです.肺・腎臓・肝臓など身体のあらゆる臓器が発育の途中にあり機能が未熟です.また,身体の機能の調節のしかたもうまくありません.しかも,発育に伴ってこれらの機能はどんどん変化してゆきます.このような子供の特徴を十分に知った上で手術前後の治療をしなければなりません.薬の使い方・点滴のしかたなどあらゆる面でおとなの常識は通用しません.これが小児外科という分野が独立して成立している大きな理由です.
また身体の発育だけでなく,こどもは精神的・心理的にも発育の途上にあり,この点も十分に考慮しなければなりません.手術という,こどもにとっては大きな試練を無事に乗り切るための精神・心理的な援助も小児外科医は考えています.
こどもについての専門的な知識を持った外科医,それが小児外科医であり,将来をになうこども達を誇りと情熱をもって治療しています.
- 小児外科ではどんな病気を治療するのか?
-
小児外科はもう少し詳しくいえば「小児一般外科」です.一般外科の受け持ち範囲は呼吸器(気管・肺など)・消化器(食道から肛門までの消化管・肝臓・膵臓など)・その他のお腹の中の臓器(腎臓・脾臓など)・皮膚軟部組織(皮膚・皮下組織・筋肉など)などです.これらの臓器の外科的な病気,腫瘍などを治療します.
泌尿生殖器(腎臓・尿管・膀胱・外陰部など)はふつう泌尿器科の守備範囲ですが「こどもはおとなのミニチュアではない」という言葉はここでも通用します.小児泌尿器科学会が結成されこどもの特性をよく知った小児泌尿器科医が育ちつつありますが,まだまだ日本全国に行き渡るまでにはいたっていません.小児泌尿器の勉強をしっかりとした小児外科医がこれらの病気を取り扱っている施設も少なくありません.小児外科医が泌尿器の病気を取り扱う理由がもう一つあります.直腸肛門奇形は新生児の病気としては多いものですが,この病気は泌尿器の奇形が同時にあることがほとんどです.その他の病気でも泌尿器系の異常を伴っていることが多く小児外科医は泌尿器系の知識も持っていなくてはなりません.
心臓・大血管の病気は心血管外科医の守備範囲で,小児外科では取り扱わないのがふつうですが,施設によってはそれぞれが独立せず一つの科になっているところもあります.したがって心血管外科も小児外科学会の重要な分野になっています.
整形外科の病気は小児外科で扱うことはほとんどなく,専門の整形外科医が扱います.また,脳神経外科の病気も小児外科の対象ではありません.
- 小児外科の患者さんはこどもだけ?
-
小児は0歳から15歳まで(16歳未満)とされるのがふつうです.つまり新生児期・乳児期・幼児期・学童期・思春期の病気を扱うのが小児外科です.このうち新生児外科は小児外科の特色を最もよくあらわした分野で,日々変化するからだの状態を理解しながら管理してゆかなければなりません.
小児期の病気を治療するので患者さんはこども中心になるのは当然です.しかし,おとなになってからでもこどものときの手術が関係する病気は小児外科医が診る必要があります.小児外科で手術する病気については成人外科医や内科医は詳しくないことが多く.その病気の特性についての理解が十分にできないからです.小児外科の技術が進歩し,歴史が深まるにつれてこどものときに手術を受けたおとなが増えてきています.小児病院ではこの人達が病気になったときに収容できる設備と制度が十分でないことが問題となりつつあります.早急に解決すべき問題として学会が取り組む課題の一つです.
また小児期に低酸素脳症の後遺症などで重度の精神運動発達遅滞となって成人期を迎えた方も小児外科の治療対象となることが多くあります.経口摂取が十分に出来ない方に対し胃瘻を造設したり,胃食道逆流がある場合に必要に応じて逆流防止のための手術を行ったりします.こういった方々に対して外科的な治療や術後の管理、退院後のフォローアップを行う場合,成人期に達した方でも多くは小児外科が治療の主体となります.
- 甲状腺の手術の後に声がでなくなると聞くが本当か?
-
甲状腺の手術の際には、声帯運動をつかさどる神経(反回神経・上喉頭神経外枝)の操作が必要になり、手術操作の際に神経の障害が生じることがあります。神経の障害が生じると声のかすれや大きな声が出せない、きれいな声がでないなど声に関する声帯の麻痺症状が出現します。また飲み込む時にむせたり咳がでたりすることもあります。しかし多くの場合には、数か月すると改善してきて術前に近い状態に戻っていきます。当科では術中に神経温存をより高くするために神経モニタリング装置を使用しています。また神経の離断が生じた場合には再建手術も行っております。声や嚥下については、最大限に配慮しています。
- くびのきずを目立たなくする方法はあるか?
-
くびのきずには最大限に配慮します。くびのしわに沿った切開をおいたり、術後の瘢痕が少ない縫い方をします。またくびの筋肉の萎縮も最小限に抑えるように神経温存に配慮してます。最近は、鏡視下手術(カメラを用いた手術)を導入し頸にきずが残らないようにすることも可能となってます。
- 甲状腺癌と診断されましたが、絶対に手術をしないといけないか?
-
手術をせずに様子をみることが可能な場合もあります。特に1cm以下の小さなもので浸潤やリンパ節転移がなければ経過観察を提案することも多いです。十分に話し合いを行った後に手術をするか経過観察するか決めていきます。