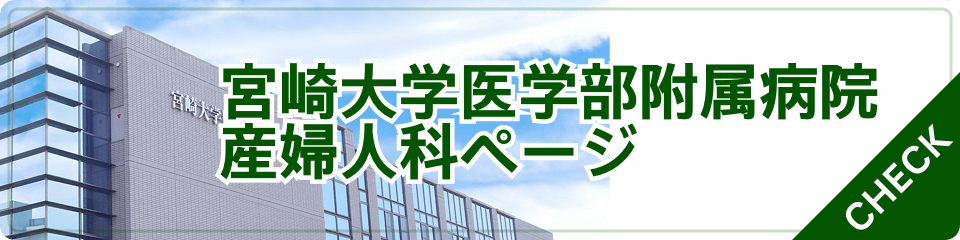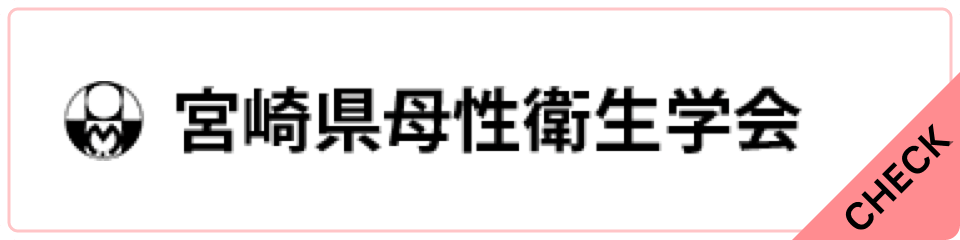清花際も無事に終わりましたね。私は学生時代ラグビー部でした。模擬店では今は『トマト鍋』になっていますが、その当時も『水炊き』でしたのでほぼ、30年前と同じメニューを続けています。他に変わっていないのが、硬式テニスの『焼きそば』剣道部の『焼き鳥』サッカー部の『綿菓子』などでしょうか。
今年、11月16日にクイズ企画の日、昼過ぎに清花際に行って大分食べました。①ボート部 おでん4種盛り 〇卵があって良かったです。②軟式テニス部 うどん 〇好きな味付けでした。美味しかったです。 ③バレー部 〇スープ餃子 ピリッと辛目が効いて良かったです。寒い日だったらもっと売れたのにですね。④ヨット部 アメリカンドック・・〇コンビニでも3年に1回位は買います。時々食べると美味しいですよね。⑤陸上部 ハッシュドポテト 〇アツアツで美味しかったです。 これだけ食べたので、我がラグビー部ではさすがに食べれなかったです。また来年ですね。
すずかけ太鼓部医学科3年生の越地媛耶(こしじえんや)さんに自己紹介して頂きます。越地さんはすずかけ太鼓を支える周囲と良く協力しあう、熱心な部員の一人です。越地さんには①宮崎、宮崎大学の魅力 ②すずかけ太鼓部でどんな事を学んだか ③どんな医師を目指したいか の3点に関して書いて頂きました。
①宮崎、宮崎大学の魅力 宮崎の魅力は冬の空の美しさです。冬は晴れている日がとても多く、空がぐっと高く広がって見えます。特に朝は格別で、通学中に空を見上げると、今日も1日頑張れるような気がしてきます。また食べ物も魅力の一つで、ご飯がおいしい上に、外食すると「いっぱい食べてね」と言わんばかりのボリュームで、そこに県民性というか、“お腹いっぱい幸せになってほしい”という気持ちが詰まっている気がします。料理の味だけじゃなく、人の優しさまで加わった“おいしさ”が感じられる場所。それが宮崎の大きな魅力だと思います。
宮崎大学の魅力は、“医師になる”という同じ目標に向かって学ぶ仲間がいることです。同期や先輩方が真剣に勉学に取り組む姿を見るたびに、自分も頑張らなければと気が引き締まります。授業や部活動の中でも互いに情報や勉強法を共有し、励まし合いながら切磋琢磨できる環境が整っており、一人では経験できない刺激や成長の機会を日々得ることができています。こうした仲間とともに学び、支え合える環境こそ、宮崎大学の大きな魅力だと感じています。


②すずかけ太鼓部でどんな事を学んだか すずかけ太鼓に入部して一番大きかったのは、同期という存在の大切さを知れたことです。ハードな練習スケジュールの中で、思うようにできず落ち込んだこともたくさんありましたが、それでも私がずっと、すずかけ太鼓を大好きでいられたのは、いつもそばで支え、励ましてくれる同期の存在があったからだと思います。
同じ曲を叩く同期とは、できない部分や悔しさを共有しながら、「ここが難しいよね」「もう少し頑張ろう」と声をかけ合い、必死に食らいついてきました。うまくいかない時も、「一人じゃない」と思えることが、どれだけ心強かったか言葉では言い尽くせません。
一方で、違う曲を叩く同期も私たちの練習をきちんと見てくれて、客観的に分析し、的確なアドバイスをくれました。その中でも「媛耶はここめっちゃよくなったよー!ここをこうしたらもっとよくなると思うよ」と、必ず良いところを見つけた上で伝えてくれたことがとても印象に残っています。練習の合間の休憩時間、自分たちもきっと疲れていたはずなのに、それでも時間を割いて声をかけてくれたその優しさに、何度も救われてきました。
来年は4年生となり、看護学科や本学の同期が卒業していく姿を見送る年になります。喜びと寂しさが入り混じる中で、共に過ごした時間の大切さをより改めて強く感じています。だからこそ、同期と一緒にいられる時間を当たり前だと思わず、ひとつひとつ大切にしながら、これからもたくさんの思い出を作っていきたいです。

③どんな医師を目指したいか 私は患者一人ひとりに寄り添い、身近な存在として気軽に相談できる医師になりたいと考えています。私自身中学生の頃病気をしていた時に、担当医から
「病気をしたからといって、医師になる夢を諦めてはいけないよ」
「大丈夫。絶対に治すから。」
と声をかけてもらったことがあります。その言葉は、先の見えない不安の中にいた私にとっての希望の光でした。医師の言葉に救われた1人の人として、今度は私がひとつひとつの命に真摯に向き合い、患者さんが前を向いて歩き出せるよう、手助けできる医師になりたいです。
以下はすずかけ太鼓部顧問 桂木の感想
宮崎は本当に晴れた冬の日が多いですね。高く澄んだ秋・冬空から頑張れと応援されているように私も感じます。食事が満たされる事はとても良い事です。『衣食足りて礼節を知る』と言います。世界を見渡せば、食事が満たされる事は当たり前ではないことは一目瞭然です。紛争による避難民の発生や農業生産の停止など世界には数多くの貧困問題があります。宮崎大学医学部生であっても貧困に苦しむ事は十分考えられます。それを感謝する越地さんの感想は医師として貧困のみならず、さまざまな悪条件を伴う患者様を日々診療する私達としてはとても胸を打つものがあります。周囲の環境、人に感謝する事から自分の希望や意欲が生まれてきます。益々、頑張って下さいね!
②の部分では同期の優しさに何度も救われたと書かれています。「媛耶はここめっちゃよくなったよー!ここをこうしたらもっとよくなると思うよ」と、必ず良いところを見つけた上で伝えてくれたことがとても印象に残っています。と書かれています。私は産婦人科30年目を迎えました。今ではこのように「真司、ここよくなったよー!」と若者らしく声を掛けられることは滅多にな経験しなくなりました。しかし、産婦人科診療においては「日々此れ前進」であり、良き60代に向かって、産婦人科教授として教室を良くするための日々の研鑽は決して絶やせるものではありません。周囲から応援されやすい「媛耶さんの雰囲気」また、それに感謝し、ありがたいと強く思っている「媛耶さんの気取らない性質」これは財産ですので、これから迎える高学年、医師人生においてしっかりと持ち続けて欲しいですね。
私がひとつひとつの命に真摯に向き合い、患者さんが前を向いて歩き出せるよう、手助けできる医師になりたいです。⇒私自身も今でもそう思います。出生して生まれてきた時は自分では呼吸位しかできなかったけれど、私たちは、医学部に合格し、数々の難関の試験を乗り越えて、国家試験に合格し医師になります。どの診療科でも患者さんを助ける、光を届ける、少しでも役に立つ存在となる、のが私達医師の使命と思っています。
越地さんを含め宮崎大学医学部の皆さんが、日本の将来を支える立派な医療者になる事を願っています。