|
フロンティア科学実験総合センター長に就任して
|
|||
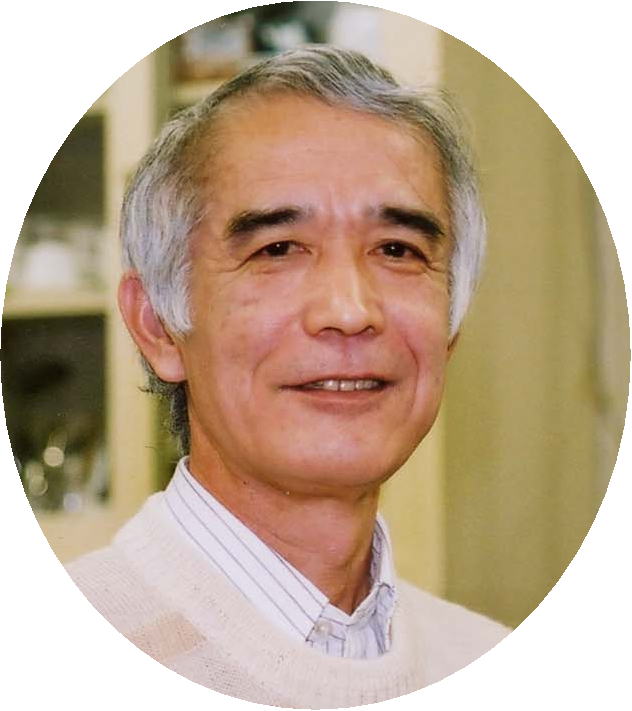 |
|||
| センター長 中 山 建 男 | |||
平成15年4月1日、本学に新たに設置された「フロンティア科学実験総合センター」の初代のセンター長に就任することになり、自他とも管理能力に欠けると認めている私としては、その責任の重さを痛感しているところです。 まず、本センターの立ち上げにご尽力頂いた文部科学省の担当官のみなさん、生みの親である松尾壽之学長をはじめ、直接、間接に携わって下さった本学の教職員のみなさんに感謝の意を表します。普通、この小文は就任に当っての抱負が通例のようですが、ここでは、「生命科学研究部門」と「実験支援部門」の2部門で構成される「フロンティア科学実験総合センター」の誕生までの経緯や目的とする業務内容の概略などを記したいと思います。
宮崎医科大学は宮崎大学と平成15年10月を目途に統合します。この新生大学の将来構想でもある大きな理念の1つは、「生命科学に特色を持つ大学の創造」です。この理念を具現化するための「生命科学研究」のコアとなる組織が「フロンティア科学実験総合センター」です。21世紀は「生命科学」の時代と良く言われます。これは紛れもない事実です。では、何故、今、宮崎の地に「フロンティア科学実験総合センター」なのか? 本学の世界に誇り得る最も大きな業績としては、松尾学長(前・生化学第二講座教授)の強力な指導の下に推進されてきた「未知の生理活性ペプチドの探索研究」が挙げられます。特筆すべきは、1983年の心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)の発見からBNP,CNPの発見と続く、ナトリウム利尿ペプチド・ファミリーの研究です。この生理活性ペプチドの探索研究は、さらにアドレノメジュリン(AM)やグレリンの発見へとつながります。このように、本学はペプチド性の生理活性物質の探索研究の分野で、常に世界のリーダー役を果してきたことは周知の通りです。これらの研究業績が認められ、平成14年度の21世紀COEプログラムの生命科学分野で本学の「生理活性ペプチドと生体システムの制御」が採択されました。また、このようなペプチド研究の実績を踏まえて、統合問題が具体化する以前から、本学独自に「生理活性物質探索研究センター」構想などを立案し概算要求を行ってきました。一方、昨今の日本の経済状況なども反映して、全国の大学で共同利用施設などの統廃合や再編が進んでいます。このような中で、今回の統合問題を契機に一気に具体化したのが「フロンティア科学実験総合センター」です。
「実験支援部門」は既存の附属施設を有機的に連携・再編するものです。現時点では「生物資源分野」および「RI実験・機器分析分野」の2分野は本学の「動物実験施設」および「実験実習機器センター」がそれぞれ移行しただけですが、統合に際して、宮崎大学の「遺伝子実験施設」、「機器分析センター」、「アイソトープセンター」も加わって、「生物資源分野」、「分子生物実験分野」、「機器分析分野」、「RI実験分野」の4分野に再編・整備される予定です。このように、両大学の4つの文部省令施設と1つの学内措置のセンターを統合した「支援部門」は新生大学の両キャンパスの先端的な生命科学領域の研究はもちろんのこと、教育・研究全般に渡る実験支援を従来よりも効率良く行える体制を整えることができるものと考えています。両キャンパスにまたがるこの共同利用施設を全ての構成メンバーが有効に活用することによって、お互いの交流、情報交換および相互作用を積極的に促進し、それぞれの教育・研究の成果をあげられることを強く望んでおります。
「生命科学研究部門」は新生大学の理念の1つである「生命科学の創造」を実践する核となる組織であり、「生理活性物質探索分野」、「生体機能制御分野」、「生命環境科学分野」の3分野で構成されます。地球生物環境の中で、ヒトを含む生物がどのように生き、どのような相互関係を営んでいるかを、分子から個体、外部環境との関わりまでを一貫した視点で解明することを使命とします。具体的には、「生理活性物質探索分野」はこれまでの研究の特質・実績を活かした、新規のペプチド性生理活性物質の探索研究、「生体機能制御分野」は生理活性物質による細胞・個体レベルでの生体システムの制御の解明研究、「生命環境科学分野」は個体と環境との関わりの解明研究、などを目標にしています。また、これらの研究内容は先に記した21世紀COEプログラム「生理活性ペプチドと生体システムの制御」の中核をなすものです。 「生命科学研究部門」の教授ポジション4のうち、3つは基礎医学講座からの振り替えであり、残り1つは文部科学省の特段の配慮による純増です。「研究部門」の核である「生理活性物質探索分野」に教授2を配置することによって、本学の創設以来の伝統であり、新生大学の目玉でもある「ペプチド性生理活性物質の探索研究」を強力に推進する研究体制を構築することができ、さらに、これによって他の多くの領域の研究も牽引できるものと考えています。この結果、将来も高いアクティビティを維持し、国際競争力を持ち、世界の最高水準の研究業績を発信し続けることができる個性輝く大学の一翼を担えるものと確信しています。 以上のように、「フロンティア科学実験総合センター」は先端的な生命科学研究の先導役を担う「研究部門」と教育・研究全般の実験支援を担う「支援部門」という、ある意味ではかなり性質の異なる2つの部門を一元的にまとめた、日本では極めて珍しい形態です。また、統合時には専任の教官数が教授4人、助教授4人、助手6人の合計14人、支援職員数が学内措置も含めて技官、事務官が11人、非常勤職員が5人程度から成る、全国的にみてもかなり大きな規模のセンターになる予定です。事実、研究の側面からみますと「研究部門」の4人の専任教授のグループ、「支援部門」の4人の専任助教授のグループの合計8つの独立した研究グループを擁することになります。さらに、新生大学において、教育・研究に直接関わる教職員が両キャンパスにまたがって所属する唯一の組織でもあります。 新しい大学の創生、法人化など未曾有の荒海を航海することになる産声をあげたばかりの赤子である「フロンティア科学実験総合センター」の舵取り役が全うできるかどうか一抹の不安を感じているのも事実です。本当の意味での初代センター長は生みの親である松尾学長であり、私は次の若い世代へのつなぎの役である2代目と心得ています。宮崎の地で新たな試みとしてスタートしたこの「フロンティア科学実験総合センター」が順調に成長し、近い将来、さらに裾野を広げて発展できるかどうかは、ひとえに宮崎医科大学の(もちろん、統合後は宮崎大学も含めた)全教職員・大学院生・学生のみなさんの力強いサポートにかかっています。なにとぞ、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。 |
|||
目 次 次へ進む 前へ戻る |