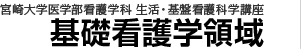教育 (EDUCATION)
学部教育 Undergraduate Education
主な担当科目
-
- 解剖生理学(1年次)
- 解剖生理学演習(1年次)
- 栄養生化学(1年次)
- 栄養生化学演習(1年次)
- 臨床病態学(疾病の成因と生態防御)(1年次)
- 大学教育入門セミナーN(1年次)
- 看護学原論(1年次)
- 看護理論(1年次)
- 基礎看護技術Ⅰ(看護共通技術)(1年次)
- 基礎看護技術Ⅱ(日常生活援助技術)(1年次)
- 基礎看護学実習Ⅰ(1年次)
- ひむか看護実習Ⅰ(1年次)
- 看護関係法規(2年次)
- 看護過程(2年次)
- 基礎看護技術Ⅲ(フィジカルアセスメント/診療を支える看護技術)(2年次)
- 基礎看護学実習Ⅱ(2年次)
- 看護管理学(3年次)
- 看護研究I(看護研究基礎)(3年次)
- 医療安全論(3年次)
- 看護教育発達論(4年次)
- 症状・徴候からみるフィジカルアセスメント(4年次)
- 総合実習(4年次)
- 看護研究Ⅱ(看護研究演習)(4年次)

特色ある教育
「地域」の視点を育てる講義・実習科目 (クリックすると詳細を閲覧できます)
「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」および「看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」の改正(第5次カリキュラム改正)において、看護の対象となる人々の「暮らし」や「地域」の理解を深める科目を強化することが求められています。そこで宮崎医学部看護学科では、宮崎県で暮らす人々の暮らしや地域について学ぶ「ひむか看護論(1年生対象)」「ひむか看護実習Ⅰ(1年生対象)」「ひむか看護実習Ⅱ(3年生対象)」を令和4年度から新設しました。
この科目では、看護の対象となる人々の生活とその基盤となる「地域」に主軸を置きながら、看護学科の教員だけでなく、地域資源創成学部や教育学部の教員、さらには自治活動や労働、報道、安全といった地域生活を支える方々にもご協力いただきながら、講義・実習を行います。「ひむか看護実習Ⅰ」については、当領域の教員が科目責任者を担当しており、地域・在宅看護学領域と合同で行っています。
詳細はこちら

<「ペロリ鉱山農園」で、学生が地元住民の方と交流しながら、米良糸巻大根の種を鞘から取り出している様子>
ポータブルエコーを用いたフィジカルアセスメント演習 (クリックすると詳細を閲覧できます)
近年、看護の世界でも、エコーを積極的に活用し、安全・確実な看護ケアにつなげようという動きが活発になっています。実際に臨床では、静脈内採血や在宅での排便・排尿管理などですでにポータブルエコーが活躍しています。本学看護学科では、令和3年度にポータブルエコーを成人・老年看護学領域が導入し、成人・老年看護学領域と基礎看護学領域が連携しながら、ポータブルエコーを取り入れた講義・演習を計画してきました。
当領域では、看護学科2年生に対する講義「基礎看護技術Ⅲ」の一部で、ポータブルエコーを用いたフィジカルアセスメントの演習を取り入れています。本講義では、対象者の体内の状態を画像により可視化することで、解剖・生理に対する知識を深めることはもちろんのこと、対象者の状態を適切にアセスメントするためのスキルを身につけることをねらいにしています。

<エコー診の演習の様子>
大学院教育 Graduate Education
主な担当科目
-
- 基盤システム看護学特論
- 基盤システム看護学演習Ⅰ
- 基盤システム看護学演習Ⅱ
- 生体システム看護学特論
- 生体システム看護学演習Ⅰ
- 生体システム看護学演習Ⅱ
- 看護教育実践論
- 看護管理実践論
- 看護情報論
- 看護研究方法論
- 研究者育成特別研究