|
日野原重明先生講演会から
|
|
医学科6年 鮫 島 直 樹 |
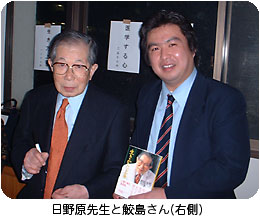 去る2月11日、聖路加国際病院理事長の日野原重明先生をお招きして、本学講義棟303教室にて「医学生、看護学生の学習の基本的転換」というテーマで講演をして頂きました。当日は学生、教官合わせて150名を越える出席を戴きましたが、都合が悪く来られなかった方もあろうかと思い、この場をお借りして講演内容を御紹介させて頂きます。 去る2月11日、聖路加国際病院理事長の日野原重明先生をお招きして、本学講義棟303教室にて「医学生、看護学生の学習の基本的転換」というテーマで講演をして頂きました。当日は学生、教官合わせて150名を越える出席を戴きましたが、都合が悪く来られなかった方もあろうかと思い、この場をお借りして講演内容を御紹介させて頂きます。本年92歳となる日野原先生は山口県に生まれ、昭和12年に京都大学医学部を卒業されました。4年後聖路加国際病院に移られ、以後、65歳まで同院で内科医として勤務され、院長、聖路加看護大学長を歴任されました。現在は同院理事長、看護大学の名誉学長を勤める傍ら、現役の医師として診療もされ、また、多数の執筆活動もこなされ、精力的な日々を送っておられます。 先生が今回の講演中に繰り返されていたことは、日本とアメリカの医療システム、医学教育システムの違いでした。(以下は先生の発言の要約です。) “日本が保険制度上、投薬、検査をすればするだけ儲かる仕組みになっているため、長期入院、重複検査、過剰投薬が横行し、一方で利潤の上がりにくい外来は3分診療になっています。保険審査をシビアにしつつ、医師以外の医療スタッフとの分業による効率化を進めればよいでしょう。また、患者の教育も行い自宅でできる簡単な検査などは自分で行ってもらったり、電話で病状を報告してもらったりして頻繁な外来受診を減らせば、もっと一人の患者を丁寧に診られるでしょう。 アメリカと日本では医療全般に関して20から30年の開きがありますが、主たる原因に、日本でのお粗末な教育があると言えましょう。日本ではスライド教育、講義主体、見学主体の教育ですが、一方ハーバードでは、まず本物を見、講義形式は殆どありません。学生は自分で調べることで知識を身に付けます。また、医学生、レジデント、フェローの間で屋根瓦式の指導を受ける形式が確立しており、近い将来のモデルを間近に見ることができ、目標が明確になることでmotivationが高まるのです。常勤の教授から講師レベルまでの職員数は、アメリカでは、学生1人に対して1.5人もいます。また、内科の教職員数で見ますと、日本では比較的人数的に豊富な京都大学ですら教授は8人、助教授は8人、講師10人、助手28人なのですが、ハーバードでは教授93人、助教授(準教授)232人、講師(助教授)420人、助手(講師)735人であることを考えますと、日米で診療、教育、研究で差が開くのは当たり前と言えましょう。にもかかわらず大学の合併統合で、人員削減が叫ばれていて、増えることは考えられることがないのです。 これからは、EBM(Evidence Based Medicine)に基づいた教育をしていかなければなりません。アメリカでは、NASA、航空機のパイロットのトレーニングで最初に使用されたシミュレーターが、医学教育でも利用されています。様々な体格の患者の挿管、静注、カテーテル留置などの技法や、手術中の体液バランスやバイタルの変化とそれに対する処置をシミュレートするのです。日本ではコストを理由に作っていませんが、日本の企業の技術者と医師が共同でシュミレーションシステムを作って、医師のskill upを目指さなければいけないでしょう。こうした様々な現象を判断、対処するというEBM教育は、アメリカでは基礎医学とみなされ、医学、看護学教育の1年目で教育されることです。 さて、EBMについてお話してきましたが、果たして、臨床医は方針決定に当たり、何を強い根拠としているのでしょう?方針決定において、最も重視しないといけないことは、illness(患者の主観によるもの)とdisease(客観的状態)を分けて考えないといけないということです。例えば肺炎の患者と、骨折の患者ではdiseaseとしては全く違うのですが、患者の反応としては共通の特徴があり、行動も共通性があります。つまり、患者がこの状態であることにどんな意味があるか(illness)・・・不安や、経済的な心配・・・これらデータにでてこない無形のものを医師は知った上で方針を決定しなければいけません。今まで、EBMを重視した話ばかりしてきました。しかしNBM(Narrative Based Medicine)は、患者の理解のためには不可欠です。このようにillnessとdiseaseを見分け、患者の理解を深めるには、患者と話し合うことしか方法はありません。 日本の医学はこれからどうなるか不安ですが、アメリカに右ならえ、ではなく、アメリカの良いところだけを取り入れるようにすべきです。とはいえ、教育システムに関しては日本よりはるかに優れていることは確かです。日本は医学部卒業の際に資格試験に受かればそれだけで済みますが、アメリカでは医学部2年終了時に基礎医学の国家資格を取らないと退学ですし、卒業時に臨床医の国家資格をとり、レジデントで患者のマネジメントの資格を取る・・・というように3段階に資格制度が分かれています。これによって、コンスタントに勉強、トレーニングをするようになります。日本は教育も制度も充実させていかないといけません。” このような医療制度、医学教育制度の変革は一朝一夕には難しく、また国全体の問題という側面もあり、本学が今すぐ単独で行えることは、あまり多くはないかもしれません。しかし、各大学病院での平均入院日数の比較において、本学のそれはあまり芳しいものではなく、クリニカルパスの検討などは早急に進めるべき課題でしょう。また、教官数は日本の他大学に比しても少ないのは間違いないことであり、現時点ではアメリカ式の濃厚な臨床教育には遠く及ばないながらも、シミュレーターの導入等で補える部分もあろうかと思います。いずれにしましても、変わる努力を怠ればこれからの法人化時代においては致命的でしょうし、学生においても単に疾患の診断と治療の学習に留まらず、今の日本の医学・医療の抱える諸問題まで含めて学んでいく姿勢が必要かと思います。 日野原先生が、今なお医師として一線級を保つためにいろいろな面で日々精進されていることを知り、医療人になろうとしている者として襟を正さねばという思いを強く抱いた一日でした。 |
 |
目 次 次へ進む 前へ戻る |