
2002/5/24更新

![]() 輸血部利用マニュアル
輸血部利用マニュアル
| 1)血液備蓄 | ||
| (1)日赤血液センターに対する血液製剤の予約、発注、検品事務と製剤備蓄 | ||
| (2)自己血製剤、末梢血幹細胞等の品質管理と保管管理 | ||
| 2)臨床検査 | ||
| (1)ABO式(確認検査として実施)、Rh式血液型、その他の血液型 | ||
| (2)直接クームス(抗グロブリン)試験、間接クームス試験、 抗赤血球抗体スクリーニングと同定 |
||
| (3)交差適合試験 | ||
| (4)抗血小板抗体検査 | ||
| (5)その他の検査 | ||
| 3)採血業務 | ||
| (1)自己血採血 | ||
| (2)成分採血 | ||
| (3)末梢血幹細胞採取 | ||
| 4)輸血治療及び輸血に関するコンサルティング | ||
| 5)血液製剤の放射線照射 | ||
| 6)その他 | ||
| (1)低出生体重児、小児用のための血液製剤の少量分割 | ||
| (2)自己血からのフィブリン糊の製造 | ||
| (3)洗浄血小板の調製 | ||
|
製剤名称
|
容量
|
略称名称
|
保存条件
|
有効期限
|
単価
|
|
|
(200ml由来=1単位1))
|
||||||
 |
赤血球MAP2)
|
140ml
|
RC-MAP1U
|
4-6℃
|
21日間
|
5,752円
|
|
280ml
|
RC-MAP2U
|
11,504円
|
||||
 |
新鮮凍結血漿3)
|
80ml
|
FFP-1U
|
-20℃以下
|
1年間
|
5,507円
|
|
160ml
|
FFP-2U
|
11,014円
|
||||
|
450ml
|
FFP-5U
|
22,336円
|
||||
|
|
||||||
|
製剤名称
|
容量
|
略称名称
|
保存条件
|
有効期限
|
単価
|
|
| (200ml由来=1単位1)) |
|
|||||
 |
照射濃厚血小板「日赤」
|
約100ml
|
PC-5U
|
20-24℃
水平震盪 |
72時間
|
38,089円
|
|
約200ml
|
PC-10U
|
76,178円
|
||||
|
約250ml
|
PC-15U
|
114,.090円
|
||||
|
約250ml
|
PC-20U
|
151.820円
|
||||
|
照射濃厚血小板HLA
|
約200ml
|
HLAPC-10U
|
97,178円
|
|||
|
約250ml
|
HLAPC-15U
|
137,430円
|
||||
|
約250ml
|
HLAPC-20U
|
182,940円
|
||||
|
洗浄赤血球
|
200ml
|
WRC-1U
|
4-6℃
|
24時間
|
6,611円
|
|
|
400ml
|
WRC-2U
|
13,582円
|
||||
| 注1) |
血液製剤は200ml献血より得られたものをすべて1単位(1U)という.
このため、例えばRC-MAP1Uは、約140mlであるし、FFP-1Uは約80mlとなる. 1人の40ml献血由来からは、各成分製剤が2単位製造される. |
| 注2) | 赤血球MAP「日赤」には、「照射赤血球MAP」もあり、在庫によって備蓄していることもあります.時間外に血液照射をする際は、2重照射をせぬよう取り扱いに注意する必要がある. |
| 注3) | FFPには、1人の成分献血者から製造される5U製剤もあるため、必要時には予約する. |
![]()
|
1)
|
検査依頼は、午後2時までに電子カルテシステムにて依頼入力して下さい. |
| 2) | 血液型、直接クームス試験は、EDTA加採血管(EDTA-2Na:NIPRO EN)で5〜7ml採血し所定ラベル(オーダコードラベル)を貼り提出して下さい. |
|
3)
|
ABO式血液型は、予めベッドサイドで簡易判定(オモテ試験のみ)を行い、輸血部に確認検査の依頼をして下さい. |
| 輸血の可能性がある患者においては、予め外来・入院の時点でABO式、Rh(D)式血液型および間接クームス試験(「血液型検査セット」をオーダする)を輸血部に依頼して下さい. | |
| 血液製剤依頼時には、予め「輸血に関する説明と同意書」を得ておいて下さい. |
1)血液製剤の申し込みから製剤入手まで
|
(1)
|
申し込みは、輸血当日の午前10時までに必須項目を電子カルテにて入力依頼して下さい. |
||
| なお、10時を過ぎて輸血が必要となった場合には予め電話連絡(Tel:3182)の上、入力を行って下さい.連絡無く入力されていると、血液製剤の準備が出来ないことがあります. | |||
|
<1>
|
血液製剤の申し込みまでに血液型検査は済ませておいて下さい. | ||
|
<2>
|
製剤申し込みは、輸血日毎に1日使用分を依頼して下さい. | ||
|
|
血液製剤の適正使用ガイドラインに準拠して過剰請求やRC-MAPとFFPの抱き合せ輸血をせぬよう注意し依頼して下さい. | ||
| <3> | 交差適合試験用の検体は、EDTA加採血管(EDTA-2Na:NIPRO EN)で5〜7ml採血し、所定ラベルを貼り提出して下さい. | ||
| <4> | 交差適合試験用の検体は、血液型とは別の日に採血して提出して下さい(2重チェックのため). | ||
| <5> | 頻回輸血の患者においては、前回の輸血から4日以上経過した場合、新たな赤血球抗体が産生している可能性があるので、5日目毎に採血し提出して下さい. なお、検査有効日はの確認は、電子カルテの輸血歴検索からも参照が出来ます |
||
| <6> | 臨床診断名、血液型、不規則抗体の有無、輸血歴・妊娠歴、輸血同意書の有無については必ず入力のこと. | ||
| <7> | 赤血球製剤には放射線照射が必要であり、照射欄のボタンに入力のこと. | ||
| <8> | 低出生体重児等で血液製剤の少量分割を希望される場合には、依頼コメントにその旨を記入のこと. | ||
|
(2)
|
交差試験済み血液製剤の入手(連絡)について | ||
| 輸血部で交差試験完了後、製剤が準備できた時点で、病棟輸血分は使用当日に、手術分は前日に輸血部から連絡があります. | |||
|
(3)
|
血液製剤の搬送方法 | ||
 |
血液製剤の運搬には、血液製剤の適正温度管理や落下等による破損防止のため、病棟または輸血部に常置してある「血液製剤専用運搬バッグ」を使用し運搬すること. | ||
|
1)
|
|
血液製剤適合票は、使用時まで血液製剤と一緒の袋に入れておく.
|
|
↓
|
|
2)
|
|||||
|
|
血液通知書(輸血伝票)と血液製剤適合票(「血液製剤使用報告書/副作用連絡」) |
照射済みの確認
(照射シールを貼付) |
使用時、「血液製剤適票」を血液製剤の余白に貼付
|
||
 |
 |
 |
|||
|
|||||
| ↓ |
|
3)
|
ベッドサイドで、患者本人と血液製剤上に貼付した血液製剤適合票をもう一度確認し、輸血を開始する. | |
|
注:
|
適合票はシール式とし、輸血時に血液製剤上に貼付できるようにした.また血液型別の色ラインを付けた.この血液製剤適合票の変更は、輸血時の取り違えを防ぎ、異型輸血事故を防止するためのものである. | |
 |
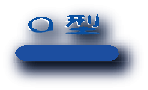 |
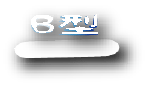 |
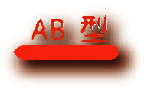 |
|
|
当院での輸血療法が適正かつ安全に行われ、血液製剤(日赤製剤および自己血製剤)の実際の使用日と副作用有無を正確に把握するために、輸血用血液製剤と一緒に添付してある「血液製剤使用報告書/副作用連絡」を製剤使用翌日に輸血部に返却する方法を実施している. |
[回収手順]
|
1)
|
輸血終了後に、切取線以下の「血液製剤使用報告書/副作用連絡」に使用日時と副作用の有無およびサイン(または捺印)を医師が記入し、病棟内の血液製剤使用報告書入れ専用ポストに入れておく. | ||
|
↓
|
|||
|
2)
|
翌日、「(病棟名)←→輸血部」と書かれた専用の袋に入れて、輸血部まで返却する. | ||
|
注1
|
医事課での保険請求計算の関係上、「血液製剤使用報告書/副作用連絡」は、必ず血液製剤使用の翌日10時までに返却して下さい. | ||
|
|
注2
|
回収が円滑に行われるように、病棟内に「血液製剤使用報告書入れ」専用ポストと回収用の「(病棟名)←→輸血部」と書かれた専用袋が設置してある. | |
|
|
注3
|
輸血中、重篤な副作用がみられた場合、速やかに輸血部に報告する. 副作用連絡書(血液製剤に添付の「血液製剤使用報告書/副作用連絡」)と共に使用した血液製剤を提出する. |
|
4) 血液の返納
|
1)
|
一旦払い出した血液及び照射済み血液は、品質管理上、返品できない.
|
| 2) |
血液製剤は、袋をとりはずしたり、マジックで記入して汚したり、適合票を貼付したりしないこと.
|
![]()
| 検査部・輸血部合同による時間外輸血検査業務を平成15年5月6日より開始しています.詳細な運用方法については、下記「時間外輸血検査の運用手順(診療科医師)」、「時間外輸血対応フローチャート」に従い対処して下さい. |
|
|
時間外に入院となった患者の血液型検査は、予め電子カルテシステムで検索のうえ、未登録の場合、検査部当日直者に依頼して下さい、 なお、依頼する際には、予めベッド再度で血型を確認の上オーダ入力して下さい. |
| 当日になって慌てることのないよう、予め外来や入院時に血型検査を済ませておいて下さい. |
↓
「時間外輸血検査の運用手順(診療科医師)」
| 赤血球MAP(RC-MAP)の検査手順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 新鮮凍結血漿 (FFP)の検査手順 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
照射濃厚血小板(Ir-PC)の場合
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【照射濃厚血小板など時間外に日赤血液センターに注文が必要な場合の手続き】
| 1) | 日赤指定の「血液製剤発注票」(事務当日直室に保管)に必要事項を記入の上、事務局当日直者に依頼してFax発注する. | |
|
|
日赤へ血液製剤発注後、患者死亡等で止むなく不要となった場合は、事務局当日直者を経由し速やかに供給停止の措置を行って下さい. |
|
| 2) | 本院に血液製剤が到着した時点で、事務局当日直者より連絡があるので、受領後、上述の手順に従い処理して下さい. この際、日赤血液センターからの納品書は、事務局当日直者に必ず渡しておいて下さい. |
|
6.手術用血液製剤の申し込みについて(Type & Screen、MSBOSの導入)
|
|
当院では、血液を無駄にせず、また輸血業務を効率化するために、手術用準備血液については、次の方法が導入されているので申込時に選択のこと. |
|
|
Type & Screen (T & S) = MSBOS 0 | |
| 出血量が500〜600ml以下あるいは輸血実施率が30%以下と予想される定型手術での準備方法で、術前に患者のABO式、Rh(D)式血液型、抗赤血球抗体スクリーニングの検査を実施し、交差適合試験を行わないで待機とする. |
||
| 輸血が必要となった時は、電話連絡され次第、直ちに交差適合試験を迅速法で実施して血液製剤を払出す. | ||
|
|
MSBOS :Maximum Surgical Blood Order Schedule:最大手術血液準備量 |
|
| 確実に輸血療法が必要とされる待機的手術の準備方法.過去に行った手術から術式別の輸血量(出血量)と準備血液量のデータを調べ、実際の平均輸血量1.5倍程度の製剤本数を交差適合試験を行い用意する. | ||
|
1)
|
実際には術式が決定したら、本院術式血液準備量の表からT&SもしくはMSBOSの本数を確認し、手術の2日前までに前述の申込方法に基づき輸血部に依頼入力する. | ||
|
2)
|
術中に輸血が必要または追加となった場合は、手術部から輸血部に電話にてその旨を連絡すること. | ||
|
|
表に記載されていない術式の場合は、従来通り記載する | ||
| 新鮮凍結血漿及び照射血小板が必要な場合は追加して入力すること. | |||
![]()
自己血輸血は、現在実施されている輸血の中で最も安全且つ副作用の少ない方法であり、その分(日赤血)を他患者にまわせるので、血液の有効利用の面からも可能な限り積極的に行うべきである.
| 自己血輸血の種類 |
|
1)
|
貯血式
|
輸血部で実施. |
|
2)
|
希釈式
|
輸血部が手術室に出張採血で実施. |
|
3)
|
回収式
|
麻酔科が手術室で実施. |
|
1)
|
貯血式自己血輸血 | |
| (1)待機期間が3週間以内の場合:CPD加採血 CPD液添加剤で採血後、赤血球と血漿とに遠心分離し、それぞれCRCとFFP製剤に製造し保存する. |
||
| (2)待機期間が3週間以上の場合や手術日が未定の場合:MAP加採血 ACD液添加剤で採血後、赤血球と血漿とバフィーコートに分離し、バフィーコートは除去後、赤血球にMAP液を加えRC-MAPとFFPとして保存する. |
||
|
2)
|
希釈式自己血輸血 | |
| 執刀直前に採血を行ない、代わりに膠質液と細胞外液を急速大量輸液をして手術室に入り、手術中あるいは、終了後に血液を戻す方法で全血輸血となる. | ||
|
3)
|
自己血小板、自己血漿などの成分採血 | |
| 自己血小板採取は、手術日の1〜2日前に行っている. | ||
|
自己採血の申込方法
|
| 1. | 全血、RC-MAP(CRC)、FFP、自己フィブリン糊について | |
| 1) | 入院患者、外来患者とも採血希望を電話連絡(内線3183)の上、採血の2日前までに、自己血採血申込書及び自己血輸血同意書を輸血部に提出する. | |
| 2) | 外来患者で血液型、抗赤血球抗体スクリーニングが未検査の場合は、血液型検査オーダを依頼しておくこと. | |
| 3) | 自己血採血の貯血量、方法については、輸血部医師(PHS:4395)と相談して選択する.なお予め本院の自己血輸血マニュアルを熟読のこと. | |
| 2. | 末梢血幹細胞採取およびその他の成分採血について | |
| 1) | 輸血部医師(PHS:4395)または輸血部看護師(内線3183)に採血予定を予め連絡しておく. | |
| 2) | 採取の7日前までに、採血申込書を輸血部に提出する. | |
| ◎感染症(梅毒反応、HBs抗原、HCV抗体、HTLV-1抗体)は、必ず事前に検査しておくこと. | ||
| ◎採血およびそれに伴う機械の操作は主治医が行うこと. | ||