
フロリダ大学研修記 医学科6年 鳥口 寛
・研修にいたるまで
「海外の大学で実習したい人はいませんか?」こんな内容のメールが大学のイントラネット"FirstClass"に掲示されたのは去年の年末ぐらいのことでした。以前からアメリカでのexternshipに興味を持っていた僕は早速それに返信しました。送信者は第一生化学教授の森下先生。僕が生化学を履修し終えた翌年に、退官された石川栄治教授に代わって赴任されたばかりの先生です。というわけで直接の面識があるわけでもなかったのですが、こんなチャンスは滅多にないと思い、思いきってメールしたのです。
学生を海外で臨床研修できるようにしたいと考えていた教授は、取りあえず試験的に学生を何人かいろんなところへ行かせて様子をみてみたいと思ったそうです。そしてメーリングリストで偶然知ったUniversity
of Floridaの外科で移植外科のassistant prof.藤田先生に、学生の世話を頼めないかということでメールしたそうです。藤田先生は森下教授と直接の面識があったわけではなかったのですが、教育担当のDr.Steinと直接電話で口頭試問に臨んでもらってそれで問題なければ来てもよいということで受け入れてくださいました。。
応募者は僕を含めて二人でして、電話会談は今年の2月くらいに行われ、二人とも合格しました。Dr.Steinは日本の民間病院で研修医相手にhistory
takingやphysical examinationを教えていることもあって、日本通でした。だから日本人にとてもわかりやすい英語を話してくれました。目前に九州・山口医科学生体育大会を控えていた僕は、春休みはラグビーに専念することにし、もう一人の方に先に行ってもらうことにしました。そして僕のほうは西医体前に部活を引退させてもらって、今年の夏休みに3週間、移植外科のexternshipに臨むことになりました。
・行程及び宿泊先
宮崎→福岡空港→羽田空港→成田空港→アトランタ空港→ゲインズビル空港
こんな複雑な経路で行かねばなりませんでした。宮崎を高速夜行バスで出発したのが夜中の11時。次の日の朝7時に空港に着き、10時の便で羽田に出発。昼前に羽田に着いてすぐにバスで成田空港へ。午後3時半の便でアトランタへ出発。およそ12時間の飛行。そしてアトランタ空港に着いたら乗り継ぎでゲインズビル空港行きの飛行機に乗り換える。エンジントラブルで二時間出発が遅れ、ゲインズビルについたのが午後10時。そこからタクシーで宿泊先であるVillager
Lodgeに向かいました。インタ−ネットで予約可能の一泊22ドルのモーテルでした。バス、トイレ、冷蔵庫、エアコン、レンジ、テレビ、ベッドつき。建物は古いし、すべてボロボロですが、気にならない人にとっては結構いいと思いました。フロリダ大学から徒歩15分。ゲインズビルはとにかく田舎。大学が三つもひしめく学生街です。人口の40%は学生だそうです。交通の便は非常に悪いです。観光スポットで有名なオーランドまでは車で約二時間。お金に余裕があったらレンタカーがあると便利かもしれません。
・研修開始
今回僕がお世話になったのがフロリダ大学医学部外科のdivisionのひとつである「移植外科」でした。以前から臓器移植外科に興味のあった僕にとっては思いも寄らない幸運でした。初日に藤田先生に迎えに来てもらい、Shands
hospitalへ向かいました。Shands hospitalというのは、フロリダ大学医学部が学生やレジデントの教育指定病院として契約している私立病院で、フロリダ大学ではこのように「付属病院」という形を取らずに私立の病院と契約して教育病院としているのです。有名なところで言うと、ハーバード大学とMGHのような関係だと思えば良いでしょう。ここで働く藤田先生は元・京都大学移植外科のスタッフで、現在移植外科でassistant
professorをされています。日本でいう「講師」クラスに値します。その上にassociate
professor、professorがいて、一番上に外科のchairmanがいます。これは各講座の教授をトップとする日本とは異なる制度かもしれません。

藤田先生とDr Stein
・研修内容
さて、いよいよ研修がはじまったわけですが、まずは移植外来から始まりました。移植を希望する患者さんへいわゆる「インフォームド・コンセント」を行う場です。日本とは違って、完全に仕切られた個室の診察室に先に患者さんを待たせます。そしてドクターが診察室へ入ります。必ずやるのがドアのノック、そして患者さんへの挨拶、握手から始まります。事前に書いてある問診表を見ながら、丁寧な問診でそれと照らし合わせ、足りない情報を加え、必要に応じて身体所見をとります。身体所見は僕も一緒にとらせていただきました。向こうの患者さんは気さくな方が多く、「日本人の医学生です」といっても嫌な顔一つしないで好意的に接してくれます。一通り終了すると、移植について具体的な説明が始まります。現在の患者さんの健康状態、移植術の利点と欠点、そして予後まで詳しく相手が納得するまで時間をかけて説明します。そしてドクターが立ち去った後にコーディネータから説明をうけ、physician
assistant(以下PA)が詳しい身体所見をとります。PAというのは立場的にはresident以上、faculty未満といった感じで、患者さんの身体所見をとり、治療計画を立て、薬の処方もできます。普通のドクターと変わらない権限をもっています。つまり万年residentといったところでしょう。はっきり言ってドクター経験数年足らずのresidentよりは物を良く知ってます。
こうして一連の手続きを終えて初めてドナー登録がなされ、患者さんはドナーが現れるのをひたすら待つことになります。

フロリダ大学の肝臓移植グループ
・organ procurement
次に「organ procurement」について説明します。これはつまり臓器の調達です。cadaveric
transplantationの時は、死亡者に病院に来てもらうわけには行かないので、自分たちで必要な臓器をもらいに行きます。何時、ドコで、誰が亡くなって、どのレシピエントキャンディデートにマッチするのか、何時、誰がもらいに行くのかを調節するのは移植コーディネータの役目です。その時点でのレシピエントの健康状態までもチェックするのが仕事です。実際にprocurementに行くのはドクターなのですが、ココの移植外科ではprocurement専門のドクターとしてプエルトリコ出身のfellowであるDr.
Solisが働いています。僕は彼にくっついて2回ほど連れて行ってもらいました。一度目はプロペラ機でジョージア州へ、二回目はヘリコプターでまたジョージアへ。どちらとも脳死患者からのliver/kidneyの調達でした。他にもう一人指導医としてDr.
Hoffmanがついて来てくれるのですが、彼がまた日本通で、日本の話題でとても楽しいひとときを過ごすことができました。実際その場に行って、勝手に手洗いもしてオペについたのですが、邪魔扱いなどされず、むしろ吸引や鈎引き、時には電メスまで握らされるという大変な経験をさせて頂きました。たまに質問が飛び交いましたが、たいしたコトは聞かれませんでした。こういった外病院でも看護婦さんや他のスタッフはやさしくて気さくな方が多く、日本からの訪問者が珍しかったのか個人的なことまでいろいろと聞かれ、それに答えるのが忙しくてあまり真剣にオペに参加できませんでした。
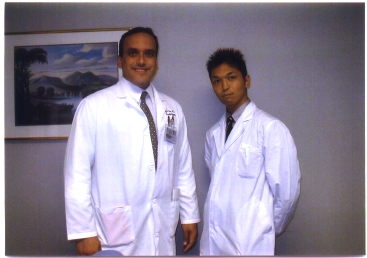
プエルトリコのDrと
・transplantation
さて、こうして調達してきた臓器をいよいよ患者さんにplantします。フロリダ大学の移植外科では肝、腎、膵移植をやっています。Donorは主にcadavar(死体)です。ちなみに心・肺移植はcardiothoracic
surgeryが担当しているようです。
毎年アメリカで脳死者から肝臓が手に入るのは年間5千件。1日にして約15件の計算です。それがフロリダ大学に回ってくるのは週に1〜2回といったところです。もちろん施設によっても地域によってもバラツキは当然あります。8時間というタイムリミットがあるので、procurementも行く場所が限られてくるからです。
移植の前に確認するべきことがいくつかあります。まずは患者の健康状態。つまり移植に耐えられる体かどうかといった問題です。特に腎移植なんかでは、術後死亡原因のトップは移植臓器不全ではなく心不全なので、特に心疾患の検索は重要だということです。
次に大事なのは患者さんのcomplianceです。移植後はそのあとの拒絶反応と闘うために、終生免疫抑制剤を飲みつづける必要があります。complianceとはつまり患者さんの自己管理の可否のことで、勝手に薬を止めてしまうような患者さんには移植をさせることはできないということです。これはコーディネータが事前に詳しく調べます。具体的には患者さんの過去の受診歴や、移植にいたらしめた疾患の現在の管理状態をみることでだいたいの予想がつくそうです。つまり、今まで自己管理ができていない患者さんは移植をしてもまた自ら駄目にしてしまう可能性が高いということです。
そして日本人にはあまりピンと来ないかもしれませんが、お金です。支払い能力のない患者さんは基本的に移植を受けることはできません。具体的にどのくらいかかるのかはわかりませんが、国民保険というものがないこの国では、保険はその人が個人的に保険会社と契約せねばならず、その保険額によって受けられる治療が限られてきます。高度な医療を受けたければそれなりの莫大な保険料を支払わなければならないのです。
僕の研修中に、移植術は腎移植が7件、肝移植5件、膵移植1件があり、そのうち腎移植に3回、肝移植に2回手洗いさせていただきました。やはりレベルが高いのか、やり方が違うのか、手術時間に日本の移植術と大きく差があります。肝臓移植に関しては、ものすごく早い人がやって2時間強、平均6時間〜7時間程度です。ちなみに日本のとある大学病院でみた生体肝移植は16時間を要していました。
・回診、カンファレンスなど
facultyを交えたスタッフ総回診は、週に2回行われます。患者さんに関するプレゼンテーションは主治医、PA、時には学生によって病室に入る直前に行われます。つまり、患者さんの疾患や治療、状態に関する情報は病室の外で話し合われ、その直後に病室に入って患者さんを診るという方式です。白衣を着ていなかったり、コーヒー片手に歩くfacultyもいますが、ディスカッションではresidentに対してかなり厳しい討論を投げかけます。
カンファレンスに関しては、肝臓移植カンファレンスなど一般的なものもいくつかありましたが、とても印象に残ったのはM&Mカンファレンスでした。M&MとはMorbidity
& Mortalityの略で死亡症例検討会です。死因に重点をおいたCPCとは違って、死亡した症例の経過に重点がおかれていて、ミスはなかったのか、もっといい方法があったのではないかといった討論を行う反省会みたいなものです。これは移植外科だけでなく、外科の全ての講座から症例をピックアップしてきて、外科研修中の学生全員も参加させての会議です。どちらかというと、学生やresidentのために開かれているといっても良いかもしれません。
主治医であったresidentが症例の経過について説明し、鑑別疾患や死亡原因など自分が調べてきたことを付け加えながら発表を進めていきます。すこしでもミスがあったり、疑問点がでてくるとすかさずchairmanや他のfacultyが厳しいツッコミをいれます。どんなに優秀なresidentもこのときばかりはタジタジです。質問は時に学生にまで及ぶことがあります。しかし、質問を投げておしまいではなく、どんなに難しいことでも学生が答えに辿り着くように、あたかも手引書を使っているかのように丁寧に誘導していきます。時には、生化学や病理学など基礎医学的な視点にたちかえりながら最終的に答えを導き出させてくれる質問の仕方にはまさに目からウロコです。今まで漠然と覚えていたことがすべて理論的につながり、一生忘れない知識となって身につくのです。
・お世話になった方々
向こうでの研修中では様々な方にお世話になりました。まずは冒頭でご紹介した藤田先生。それにtelephone
conferenceを提案していただいたDr. Stein。この方は沖縄県立中部や亀田総合など日本の民間病院で研修医相手にgeneral
medicineを教えている方で、彼のホームページにもそのコトが詳しく書いてあります。他には研修後半期にお世話になったプエルトリコのドクターや移植外科のprofessor。特にprofessorにはご自宅の夕食に招いていただくなどのhospitalityを受け、本当に感激しました。
・研修の意義について
最後にアメリカで研修することの意義について自分なりに考えたコトを綴ってみます。
アメリカ帰りの人間は日本批判に走りがちで、二言目には「アメリカでは〜〜」が口癖となって”アメリカかぶれ”と敬遠されがちになりますが、自分は少し違う意見を持ちました。
日本人医師がアメリカで研修を積むことが本当に必要かというと、答えは「No」であると思います。日本で一生やっていくと決めたのなら、わざわざ苦労してアメリカに行く必要はありませんし、日本で学んでも十分世界に通用する高度な知識と技術は身につくと思います。一般外科に限っては日本のほうがキメ細かくて技術も上であると思います。さらに保険制度や医療制度、社会情勢、地域性を考えると両国の間で大きな隔たりがあり、むしろ日本だけでやっていくほうが日本にマッチしたドクターになれると思うのです。日本でもアメリカでも良いところと悪いところが混在して、はっきりどちらが優れているとは一概には言えないと思いました。
ココまで言うとアメリカで学ぶ意義はゼロであるように聞こえるかもしれません。ただ、ある分野に限ってはアメリカのほうが前を進んでいると言わざるを得ません。移植に関して言えば、症例数、技術ともにアメリカに大きく差をつけられています。社会的背景の違いもあると思いますが、やはり何か新しくてハデなコトっていうのはアメリカが先駆者になっている場合が多く、その点は認めざるをえないのではないでしょうか。すなわち「アメリカしかやっていない優れた医療で、日本でも将来的に導入の価値があるもの」や「日本にもあるがアメリカのほうが進んでいる」と考えられる分野に限っては苦労して渡米して学んでも意義があるかもしれません。
日本人医師が臨床医としてアメリカでやっていくには数多の苦難を乗り越えなければなりません。言葉の問題、研修先受け入れの問題、帰国後の就職先の問題など山積みです。それでも渡米するだけの価値があるものを何か見出せると確信してから行くのなら、後は本人の努力次第であると僕は考えます。要は相当の努力と覚悟と情熱、そしてコネと下調べが重要だということです。
学生時代にアメリカの医学に興味をもつ方は大勢いらっしゃると思いますが、そういう方は是非学生時代に向こうでexternshipをすることをお薦めします。学生なら特に資格もいらず、医局の事情に左右されることなく、特に能力がなくても気軽に海外研修に臨めます。もちろんある程度の準備は必要ですが、勢いで飛び込んでも怖くないのが学生時代の特権だと思います。そうやって自分の目で一度見て、その上でアメリカ医学を学ぶことの意義を自分なりに考えていけば、日本でただアメリカに憧れているだけよりももっと実際的な考えを持つことができると思います。
以上まだまだ書ききれなかったことが多数ありますが、取りあえずここらへんで終わりにしたいと思います。最後になりましたが、このような素晴らしい機会を与えてくださった第一生化学の森下教授に、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。